小説(長編小説)│金貨と魔人の爪先|第四幕 1
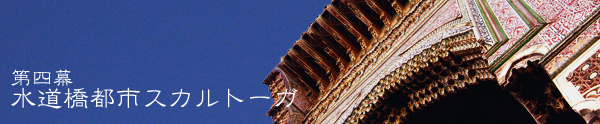
第四幕「水道橋都市スカルトーガ」
食料、鍋、毛布など、旅に必要なものを、カッカトーランは塔の屋上まで運ぶ。
駱駝の世話をしていた金貨は荷を受け取り、慣れた手つきで小さくまとめていった。
「ほう、うまいもんじゃ。よく、まとまっている」
手際を眺めていると、金貨は困惑したように唇を結んだ。
――おれも……一緒にスカルトーガに行く。
そう言ったきり、金貨は押し黙り、結局、スカルトーガ行きを望む理由を話すことはなかった。
だが、その思い詰めた様子から、スカルトーガに「なにか」があることは容易に知れた。
金貨はまだ抜糸を終えたばかりで、体調も万全ではない。なによりも、例の「干からび」のことがある。
金貨には定期的に水を飲ませ、「干からび」自体が起きないようにしているが、あれをこのまま放っておくわけにはいかなかった。
(スカルトーガにはなにかがある。そのなにかが「干からび」の原因に繋がるなら、こちらから探しに行くまでじゃ)
カッカトーランは駱駝の背に荷をくくりつける金貨を、じっと見つめた。
数刻後、すっかり旅支度を終えた二人と一壺、駱駝二頭は、屋上の中央に立った。
「さて、金貨。スカルトーガに連れて行く上での約束は覚えているな?」
「「干からび」が起きないよう、定期的に水を飲むこと。具合が悪くなったら、すぐに言うこと」
金貨の答えに、カッカトーランは満足して笑む。
「よし、それなら出発といこう! 忘れものはないか? おやつは持ったか!?」
『クッキーを持った。アーモンド入りのやつと、砂糖をまぶしたやつだ』
駱駝の脇腹にくくりつけられた白布の壺が、上機嫌で答える。
カッカトーランは「上々じゃ」と答え、屋上から下の階に伸びる階段に目をやった。
階段の陰にはサラードハザが立ち、彼らを見送るように腕を組んでいた。
「留守は頼むぞ、サラードハザ!」
カッカトーランは手を上げ、サラードハザの返事を待たずに、黄金の槍を空高く掲げた。
「それではいざ、渓谷の闇に別れを告げ……開門!」
振り下ろした石突きを、屋上に突き立てる。
半壊したままの屋上に、光によって描かれた円環が浮かび上がり、内環と外環とがそれぞれ逆方向に回転した。
そして、足元から光が迸った次の瞬間、二頭の駱駝とともに、旅人たちの姿は門番塔の屋上からふっと掻き消えた。
+++
微かな風が砂塵を巻き起こし、荒れた地表を冷たく撫でてゆく。
砂礫の上を鬱屈と歩いていた邪霊は、ゆらりと顔を動かし、闇に腐った眼を凝らした。
なにか良い香りがする。
『ア、ァア……イイ匂イ……』
骨が剥き出しになった両手足を地に這わせ、邪霊は香りの方へと足を進める。
少し離れた地平を、二頭の駱駝が列をなして歩いていくのが見えた。
邪霊は口から白い息を漂わせながら、一歩、また一歩と香りの方へ、駱駝の方へと近づいていった。
カッカトーランは駱駝の手綱を引きながら、背後をじりじりとついて来る邪霊の群れを見つめた。
さすがに門番塔の外に出てくると、邪霊の数も増える。
白布の存在に怯えて、一定以上は近づいてこないが、〈昼の民〉が邪霊の群れを見たら、恐ろしさのあまり卒倒することだろう。
だが、ちらりと金貨に視線を移しても、少年は特に気にした様子もなく歩きつづけている。
(邪霊のことは、問題なさそうじゃの)
安堵し、ふたたび顔を前に戻して、胸いっぱいに冷たい空気を吸いこむ。
カッカトーランは夜の旅が好きだった。
星の流れる音すら聞こえそうなほどの静寂は、灼熱の太陽に支配された砂漠とは対照的に、何者も拒まず、すべてを受け入れるかのような穏やかな安らぎに満ちている。
どこまでも広がる星空の円蓋を、ついと流れる銀色の細い線。
風はかすかで、駱駝の蹄が砂利を踏む音しかしない。
夜の静寂は人の声で破るにはあまりに心地よく、その無音を聞いていれば、特にお喋りで時間を潰す必要も感じず、二人と一壺は無言で夜の旅をつづけた。
空から星がひとつひとつ消え、透きとおった藍色に薄らぎはじめたころ、眼前に見上げんばかりの岩山が姿を現した。
岩肌に沿って歩くと、やがて休むのにちょうどよく、頭上に岩の庇がせり出した場所を見つけ、一行はそこを昼の仮宿と定めた。
カッカトーランは駱駝の両足を縛って遠くまで行かないようにし、金貨は石で作ったかまどに火をつくり、鍋で簡単な豆煮込みをつくり、パンを用意する。
洞の壁を赤々と照らす焚き火と、洞から立ちのぼる細い湯気。
カッカトーランと金貨、白布はそれぞれ、白い息を吐きながら温かい食事を口に運んだ。
「白布。せっかくの旅の夜じゃ、寝物語を聞かせてくれんか」
食事を終え、カッカトーランがごろりと横になって言うと、壷が楽しげに笑った。
『そうだな。金貨もいることだし、久しぶりに夜の物語をするとしようか。……金貨は、このアブラズニア半島の神話について知っていることはあるか?』
金貨は不思議そうにして首を横に振る。
『今から五二六〇年前、世界は一度滅亡した。水と緑に包まれた豊穣の地アブラズニア半島。神よりの恩寵を受け、豊かな暮らしを営んでいた民は、しかし時の流れとともに神を侮り、自らを驕るようになった。腹を立てた神は、口から吐きだした火によって大地もろとも人間を焼き払い、さらには水脈を人の手が届かぬ場所へ隠して、この地を去っていった。
それから百年、残り火がいまだ燻るアブラズニアの大地に、魔導の民が現れた。彼らは人ならざる異能によって火を鎮めると、すべてが焦土と化した大地――砂漠で、ささやかな暮らしを営むようになった。
噂を聞きつけ、いつしか砂漠には他大陸より流れてきた人々が集まるようになり、やがて〈渇きの百家〉が形成されていった。この魔導の民こそ、〈夜の民〉の始祖と言われている。
彼らのもっとも大きな功績は、もちろん神の火を消したことだが、もうひとつ、本当の意味での偉業は、神が隠した水源のありかを明らかにしたことと言えるだろう。今宵はその物語を語るとしよう」
白布は前置きの末、穏やかな深みのある声で語りはじめた。
『昔々、といっても、砂漠の砂が岩に還るほどには遠くない昔のこと。
渇きの民は、〈水の甕〉を頼りに細々と暮らしていたが、甕を満たした水は無限ではなく、尽きるたびに別の〈水の甕〉を探して旅をする必要があった。
ある日、魔導師フルドは〈水の甕〉の水がどこから来るのかを探ろうと、水にもぐってみることにした。甕の底は鋼鉄のように固く、地下水脈に通じている様子はない。水がどこから来るのかさえ分かれば、もっと民の生活は楽になる。そう考えた魔導師は、夜の帳の向こうにある異界より、〈水漣の魔人スーラギュア〉を召喚し、こうたずねた』
――魔人よ、魔人。
――この水源の見当たらぬ灼熱の砂漠で、貴女ならばどう生き抜くか』
『スーラギュアは異界の水辺に生きる魔人。水なくしては生きていけない。彼女は夜空を見つめて、こう答えた』
――私ならば、空にゆく。
『不思議に思った魔導師は、スーラギュアとともに空へと飛んだ。スーラギュアは透き通る四枚の翅を広げ、魔導師は魔道具〈空飛ぶ絨毯〉に乗って。
幾百夜、幾千夜と経ったのち、魔導師はついに水源のありかを知る。
ああ、なんたることか。怒れる神は、水を空に隠したのだ。夜空にぽっかりと穴が開き、そこから水が滝となって砂漠に落ちていく。滝は砂漠に深々と穴を掘り、砂に含まれた石英を結晶化させて適度な甕を作って水を溜める。五日が経った頃に滝は姿を消し、後にはただ〈水の甕〉だけが残されていた。
魔人スーラギュアは、生まれたばかりの〈水の甕〉で泳ぎながらこう言った』
――時折、空は水の重みに耐えきれなくなる。空に亀裂が入り、そこから水は滝となって地表に降りそそぐ。
――だから魔導師よ、最初の問いにはこう答えよう。
――私ならば、空にゆく。
岩陰の虫たちも邪霊も、白布の柔らかな声に聞き入っているようだ。
カッカトーランはうっとりと目を閉じ、金貨もまた魅了されたように、白布の壷を見つめている。
「これは、本当の話?」
ふと、金貨が小さな声で問うた。
白布は壷のうちでクツクツと笑い、『私も知らないのだ』とだけ答えた。
+++
夜明けとともに白布は眠りにつき、カッカトーランも地べたに横になる。
頭上には、満天の星空。まだ朝までは一時間ほどある。
邪霊が地を這う音、獣や虫たちの切なげな鳴き声、冷たい空気が肌に刺さり、カッカトーランは毛布に肩までくるまった。
ずいぶん経ってから、横になったはずの金貨がごそごそと身を起こす気配がした。
金貨はカッカトーランとが眠っているのを確認してから、毛布を引きずり、洞の外へと出ていく。
しばらく待って、カッカトーランはむくりと身を起こした。
金貨の姿を探すと、少年はふらふらとした足取りで、夜空の下に歩み出るところだった。